みなさんは療育場面で子どもと関わる時に、
「褒めて伸ばすのが大事」と聞いた事がある人は多いと思います。
しかし子どもと関わっていく中で
次のように悩み、考えている人は多いのではないでしょうか?
子どもを叱ってはいけない
子どもの問題を指摘することができない
子どもにストレスをかけないようにしなければならない
これらは「褒めて伸ばす関わり」がいつの間にか
「ネガティブなところを示さない」という形に変わっていっている面があります。
しかし、この「ネガティブな面を見せない」という関わりが
さまざまな問題のきっかけとなっている事があります。
今から紹介する本では、子どもを適切に叱ったりなだめたりすることを
「世界からの押し返し」と表現しています。
「世界からの押し返し」が大切である事を知ることが出来れば、
みなさんの日々の子どもの接し方が良い方向に変わってくるかもしれません。
私はこの本を読んで、
現在子どもたちが抱えている問題、学校が直面している問題、保護者の問題が
それぞれ見えてきましたし、
子どもや保護者への接し方が変わってきました。
是非みなさんにも知ってもらいたいと思いますので、
次の章から、「世界からの押し返し」について書かれた
私がおすすめする本を紹介・解説していきます。
本の概要

今回おすすめしたい本はこちらです。
タイトル:「叱らない」が子どもを苦しめる
著者:薮下遊 髙坂康雅
発行所:株式会社筑摩書房
スクールカウンセラーとして働いている著者は
多くの保護者は「子どもを褒めて伸ばす」という関わりを知っていて、
「叱ってはいけないと思っていた。」と話しているとの事です。
しかしここで著者は褒めて伸ばすアプローチは万能ではない事を指摘し、
「褒めて伸びるものもあれば、それでは伸びないものもある」
「適切に叱る事で子どもの成長を促すことができる」
と保護者に説明していると述べています。
事実、著者は子どもを適切に叱る事で子どもの不適応や問題が改善した
事例も多く経験していると述べています。
この本では、
学校現場で増加してきた子どもたちの不適応を紹介し、
それと関連が深い特徴や環境と、
それらが生まれた社会文化的な変化について紹介しています。
その上で、著者自身が対応して効果が得られた支援の方針について述べています。
本書のポイント

次に私がポイントだと思う点をいくつか紹介していきます。
1.「世界からの押し返し」についての解説
この本で述べられている
子どもの不適応と関連が深いと思われる特徴として、
「思い通りにならない事に耐えられない」というのがあります。
これは子どもが親から適切に
叱られる・止められるなどを経験していないためだという事です。
著書では親が責任を持って叱る行為を
「世界からの押し返し」と表現しています。
親から適切に叱られる経験は子どもの心の成熟にプラスに働く側面があります。
これを経験しない子どもは「思い通りにならない」という体験を積む機会がないため、
「思い通りになるのは当然」という万能感を持つリスクが高まります。
一方で、世界からの押し返しを外注するという場合も見られます。
これはつまり、親の責任で叱るのではなく他人に任せてしまう事であり、
「世界からの押し返し」にはなっていません。
例えば
「鬼からアプリ」を使って鬼に怒ってもらう
「店員さんに怒られるから」と言っていたずらをやめさせる
などがあります。
親が怒ると子どもは不快になりますが、
その不快を親子関係の中で経験し、受け止められ、なだめられるという経験が
子どもの心の成熟には不可欠だという事です。
2.子どもを取り巻く社会風潮の解説
先のような「世界からの押し返し」ができない親には、
子どもを不快する事に抵抗を示す場合が多いといいます。
このような抵抗と関連がありそうな社会の風潮として著者は
「褒めて伸ばす」という子育てにあると指摘しています。
現在の子育ては「褒めて伸ばす」が変化して
子どもに「ネガティブなところを見せない」になってしまっています。
ネガティブな面を持たない子どもはいないので、それを見せないのは
現実を作り変えている事になります。
「世界からの押し返し」とは、
こうしたネガティブな面を子どもに向き合わせつつも、
「そういうあなたが大切だ」という事をしっかり伝えるという事だと述べています。
3.子どもと保護者への支援方法
この本では著者が考える具体的支援方法についても述べられています。
子どもの不適応に対して、
まずはネガティブな側面に向き合わせることが大切だと述べています。
しかしこれは年齢などを考慮して行っていく必要があるとも書かれています。
それに子どもと保護者の親子関係や家庭環境も考えなければなりません。
これらを十分に考慮した上で
親が納得できる形で子どもの不適応のしくみを説明すると、
親が安心感を持って対応できるため、
子どもへの日常的な関わり方が良い方向に変化していきます。
こうする事で少しずつネガティブな側面に向き合いつつ
心の成熟を促していくことができると述べています。
感想
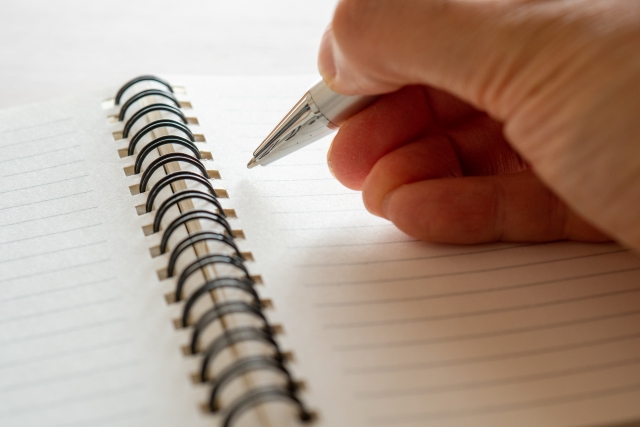
私はこの著書の大事な点は、
「適切に」叱ること
「適切に」ネガティブな側面と向き合わせること
だと思います。
本のタイトルだけ読んで
子どもを叱って育てるのは良いことなんだ
もっと子どもに出来ていないことを見せる必要があるんだ
という極端な考え方になってしまってはいけないと思います。
子どもを不必要に怒鳴ったり叱ったりするのは
心の成熟を促すものにはならないでしょう。
そしてネガティブな側面を四六時中見せつけるのは論外だと
著者がはっきりと述べています。
子どもの良い部分は褒めて伸ばしつつ、
ダメなこと、してはいけない事は自分が責任を持ってしっかりと伝える
このような姿勢が求められていると私は思います。
それに現在の「褒めて伸ばす」風潮が
「ネガティブな部分を見せない」という内容に
すり替わってきているという指摘は
大変参考になりました。
私自身が知らず知らずこうした風潮に巻き込まれてしまって
子ども達にとって大切なものは何かを見失いかけていたなと思います。
それに気付かせてくれる貴重な1冊です。
この本にはその他にもここでは書ききれない情報がたくさん詰まっています。
興味を持たれた方は是非お手に取ってみてください。


コメント