何か困りごとを抱える人たちをケアする対人援助職の人たちは、
対象が子どもか成人であるかに限らず
日々色々な事に苦労していると思います。
そうした日々の仕事の中でストレスを抱えて
苦しく感じている人も多いのではないでしょうか。
ストレスマネジメントが大切だというのは分かっていても
実際にどのようにやれば良いのか分からないという方もいると思います。
この記事で紹介する本は、
ご自身のストレスに対処したいと思っている方にうってつけだと思います。
私も対人援助職の1人ですが、
この本に書かれている考え方・実践の一部をしているだけでも
ストレスが弱まったという感覚があり、
大変役に立っています。
次の章から
是非皆さんにも活用して頂きたい著書を紹介します。
本の概要
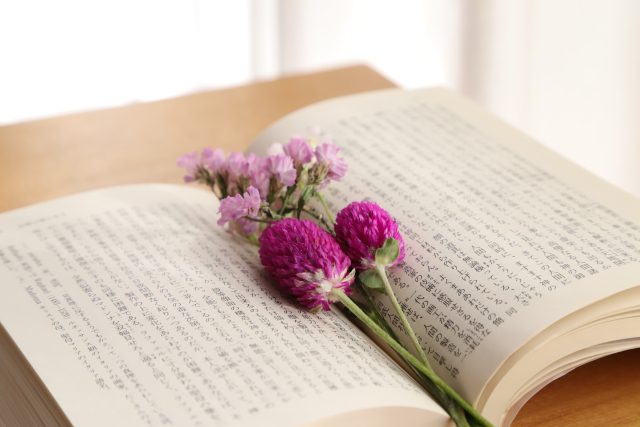
今回紹介する本はこちらです。
タイトル:ケアする人も楽になる認知行動療法入門 Book1 Book2
著者:伊藤絵美
発行所:株式会社医学書院
この本はBook1と2に分かれていて、
Book1ではタイトルにもある認知行動療法についての
基本的な考え方や手法についてが具体的に書かれており、
後半には事例紹介があります。
Book2は事例紹介だけなのですが、
認知行動療法の他にも
リラクセーション法や心理教育といった
Book1には書かれていない具体的支援方法についての記載があります。
この本の著者は、
対人援助職のストレスは他の職種に比べて深刻になりやすいと指摘しており、
他者をケアする人は自分自身のケアやストレスマネジメントを
自覚して行う必要があると述べています。
そこで著者はこの本を、
ケアを職業とする人たちに書いたとの事です。(特にナースに向けて)
自身のケアに認知行動療法を役立ってもらい、
そこから発展させて患者のケアに役立ててほしい
との思いが込められた著書になっています。
本書のポイント

私が思うポイントは以下の通りです。
認知行動療法とコーピングについての分かりやすい解説
本書は図表も用いながら認知行動療法の基本的なモデルについて説明がされていますが、
これがとても分かりやすいです。
かいつまんで説明すると
心理学ではストレスというものを考える時、
環境(どういった状況か)と個人(どのように反応するか)
とに分けて相互に影響するものとしています。
そこから個人の反応は
①気分・感情、②行動、③身体の反応、④認知の4つに分けられます。
この4つは全てつながっており、
さらに認知は環境からくる状況や出来事や対人関係の影響を受けたり、
自分から影響を与えたりしています。
これらは文字にすると分かりにくいと感じるかと思いますが、
本書には分かりやすい図があります。
また、コーピングという考え方についても解説がされています。
これはストレスに対する意図的な対処の事であり、
自分がリラックスできる方法であれば何でも含まれます。
例えば
映画を見る、好きなものを食べる、思いっきり寝るなどです。
深呼吸するなども含まれます。
しかし注意なければいけないのは、
コーピングの対象は認知と行動だけなのです。
なぜなら、
環境、気分・感情、身体反応は自分で変えることはとても難しいからです。
このような理由で、認知と行動に働きかける心理療法なので
認知行動療法と呼ばれています。
この記事では割愛しますが、
本書には他にも認知には階層構造がある事や
スキーマというものがある事について述べられています。
これらについては本書でも簡単に触れている程度ですが、
詳しく知りたい人向けにおすすめの書籍が載っています。
分かりやすいワークシート
認知行動療法を実際に進めていくためには、
ターゲットとする自身の困り事を決めて
それについて色々と分析していくのですが、
それらを独力で進めていくのは難しい面があります。
しかし本書に載っているワークシートはそこを上手にカバーしており、
大変分かりやすくまとめる事ができるものになっています。
ワークシートは先の気分・感情、行動、身体の反応、認知の4つを
詳しく書き出したり、
自分の困り事についての影響の大きさを数値化してみるといったものがあります。
感想
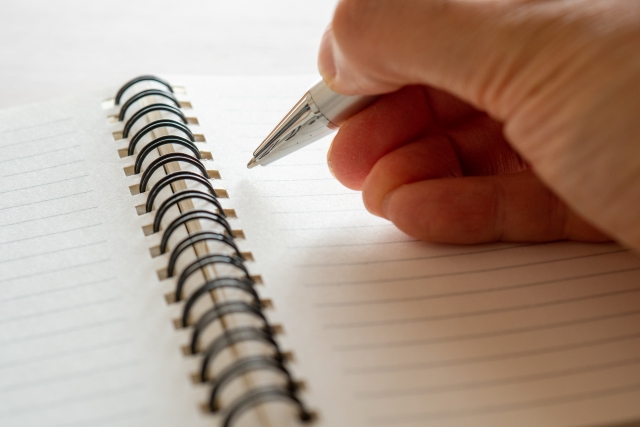
この本は認知行動療法の解説が分かりやすいのに加え、
自分もやってみよう!という気持ちにさせてくれるのが
良いところだと感じています。
ストレスケアについての本は色々とありますが、
どれも自分でやってみないといけませんので
とっかかりやすいというのが大切だと思います。
そしてこの本のワークシートに沿って作業を進めていくと、
色々と自分の悩みが整理されていく事が実感できると思います。
私の場合は、
今自分が悩んでいることは何なのだろうと紙に書き出すだけでも
良い効果があったと感じています。
自分のモヤモヤした感情やストレスを感じる環境を
文字にしてそれをながめるだけでも
一歩離れて客観的に見るとてもよいきっかけになります。
まとめ
療育に携わる人はまさしく対人援助職であり、
多くのストレスを抱えていてもおかしくはありません。
そういった方々にこの本は大変有益です。
もちろん認知行動療法を勉強してみようという方にとっても
この本は導入にうってつけです。
興味を持った方はぜひお手に取ってみてください。


コメント