みなさんは感覚統合という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
療育に携わる人であれば一度は耳にしたことがあると思います。
そんな感覚統合にみなさんはどんなイメージを持っていますか?
なんとなく遊具で遊んでいるようだけど実は何をやっているのか
よく分からないという人も多いと思います。
または、トランポリンやブランコを使うのが感覚統合だと
思っている人もいるでしょう。
セラピストであれば感覚統合を取り入れた治療を実践している人も多いと思いますが、
これを保護者にただブランコで揺れていたりトランポリンで跳んでいるだけではないと
説明するのに苦労した経験がある人もいるのではないでしょうか。
そのような人たちにおすすめしたい本があります。
感覚統合の事が分かると、
セラピストの方は子どもへの治療の引き出しが増える事は
間違いないと感じています。
そしてセラピストに限らず療育に携わる人
感覚統合の事を知ると子どものアセスメントの幅が
大きく広がるでしょう。
それは自分自身にとって大きな強みになると思いますし、
保護者に今自分がやっている事を説明できるようになるというのも
大切な事だと思います。
それでは次の章からおすすめの本を紹介します。
本の概要

今回紹介する本はこちらです。
タイトル:感覚統合の発達と支援 子どもの隠れたつまづきを理解する
著者:A.ジーン・エアーズ【Pediatric Therapy Network 改定】
監訳者:岩永竜一郎
発行所:株式会社金子書房
この本はエアーズが書いた″Sensory Integration and the Child”という本の
改訂版を訳者たちが翻訳したものです。
初版では保護者に難しいと感じさせる構成もあったとの事ですが、
改訂版は主要な内容は旧版を受け継ぎつつ、
専門性の高い項目は参考用として巻末付録に移しています。
またレイアウトを読みやすくし、
写真やチェックリスト、保護者へのアドバイス、症例、重要点のまとめ、図解などが
加えられています。
本書のねらいは
保護者のみなさんが子どもの感覚統合の問題に気付き、
何が起きているのかを理解して、
子どもを助ける行動を起こすきっかけになることだと述べています。
また子どもが感覚統合のアセスメントを受けたり治療を始めた時に、
セラピストが何をしているのかを理解するうえでも
役立つ可能性があるも書かれています。
内容は
第1章が感覚統合の概念の紹介
第2章が乳児や子どもの感覚統合の発達について
第3章は脳の働きについて
第4~9章ではさまざまなタイプの感覚統合障害について
第10章で感覚統合機能改善を目的とした治療について
第11章で子どもの理解と支援のために家庭でできること
これらが紹介されています。
本書のポイント

私が思うポイントは以下の通りです。
感覚統合で重視している感覚の事が分かりやすい
私たちは感覚についてを
いわゆる五感で説明されると理解がしやすいと思うのですが、
感覚はそれ以外にも存在しており
そちらも感覚統合には重要だと言われてもピンとこないという方も
いると思います。
その分かりにくいのではないかと思われる感覚には
「前庭覚」と「固有受容覚」がありますが
これらについて丁寧に説明されています。
かいつまんで紹介しますと、
前庭覚は自分の頭の位置がどのような向きになっているのかや
どれくらいの速さで動いているのかといった情報のことです。
固有受容覚は筋肉が今どれくらい縮んでいるまたは伸びているのか
という情報のことです。
感覚統合ではこれらの感覚の情報を重要視しているため、
前庭覚や固有受容覚がどういった種類の情報なのか、
運動時にどのような役割を担っているのかを
知っておくことは重要です。
特に前庭覚については、
その感覚情報がうまく処理できない事で起こる問題について
たくさんの解説がなされていますが、
難解な部分も多いです。
その点についての解説を本書では紙面を多く使っています。
保護者に向けたアドバイスとチェックリストが分かりやすい
この本は第5~8章で子どもの気になる行動についてを
確認できるチェックリストがあります。
そのチェックリストは前庭覚・触覚・視覚などがあり、
子どもの気になる部分をピックアップするのに役立つと思います。
ほぼすべての感覚刺激を網羅しているので子どもの様子も捉えやすいです。
保護者だけでなく療育機関のスタッフにも
子どもの様子を把握するのに役立つものだと思います。
また保護者へのアドバイスも章末に載っているのですが、
書かれている関わり方や活動内容はかなり具体的で、
普段の療育場面で取り入れられているものばかりです。
活動の方法についての情報がほしい時は
十分活用できると思います。
感想
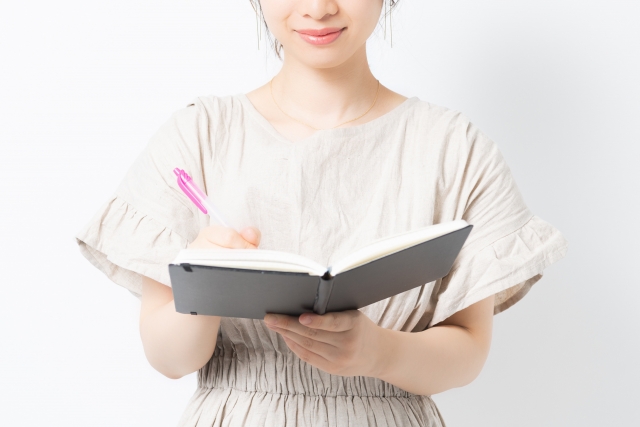
この本は感覚統合を知るための本の中では
入門レベルの内容よりも掘り下げて説明しているのかなと思います。
感覚統合の事を勉強しようと思った方が
読む本として選んでも良いかと思いますが、
最初は他の入門的な本を読んでからでも良いのかなと思います。
そうする事で
本書で詳しく書いてある内容の理解がしやすいでしょうし、
子どもへの関わり方・遊び方に結び付けやすいと思います。
感覚統合を日々実践している、またはその予定だという方は
この本から入っていっても良いと思います。
この本に書いてある保護者に向けたアドバイスには
子どもと関わる際の活動に含めたい要素(リズムのあるもの、自分で動きを考えるなど)が
紹介されているのですが、
これは普段作業療法士が用いている遊びと一緒のものがたくさんあります。
この本を読んで知識を持って活動を実施できれば
とても療育の幅が広がっていくと思います。
入門から感覚統合の理解のステップを進めたいという
療育関係者にはうってつけの本です。
この本は最初の章に
保護者が感覚統合に問題を抱えていると思われる子どもに
どのように関わっていけば良いのかが書かれています。
そこには特別な視点で子どもを見る必要はなく、
環境を整えてあげる、専門家の支援を求めるなどごく一般的な事を紹介しています。
これはどれだけ専門的な知識を持とうとも
決して忘れてはならない基本的で重要なことなんだと改めて感じる事ができました。
子どもの事で困っている方々に
日常的に意識して伝えていきたい内容になっています。
まとめ
著書「感覚統合の発達と支援 子どもの隠れたつまづきを理解する」は
子どもの運動や気になる行動に悩んでいる保護者にとって
大変参考になる本だと思います。
また、感覚統合をもう少し掘り下げてみたいと思っている方にも適している本です。
興味を持った方は是非お手に取ってみてください。


コメント