療育に携わっていると、
それが子どもないし大人が言ったに限らず、
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)の方々の
行動や話している事を疑問に思った事があるのではないでしょうか。
どうして言葉の意味が伝わりにくいの?
不注意によるミスが多いのはなぜ?
特定の感覚が感じにくいとどんな生活になるの?
このように思った事のある人は多いと思います。
そんな時にみなさんはきっと
発達障害の当事者の方が書いた本を読んで調べる事が多いと思います。
今はたくさんの本が出版されていて参考になるものもたくさんあります。
私もそれらを読んで、その都度新しい発見をしています。
今回紹介する本も当事者の方が書いた本なのですが、
これまでのものとは少し違った書き方の本になっており、
それが面白いなと感じます。
次の章から、
みなさんにおすすめしたい本を紹介します。
本の概要

今回紹介する本はこちらです。
タイトル:みんな水の中 ー 「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか
著者:横道誠
出版社:株式会社医学書院
この本はASDとADHDの診断を受けている著者が、
Ⅰ部「詩のように。」、Ⅱ部「論文的な。」、Ⅲ部「小説風。」という
3つの様式を使って自身が体験している世界を伝えるのが
目的だと述べています。
また著者はこの本について、
色々な本の影響を受けて執筆している事を認めつつも、
先の3つの様式で自分自身に迫ろうとしたこと、
自助グループおよび文学と芸術によるケア、セラピー、リカバリーという
見通しを示した事は本書の大きな特徴だと述べています。
文学の専門家が文化人類学から学んだ手法で自身のフィールドワーク記録を作ったり、
哲学や言語学から学んだ知識も使って医療・福祉を考えたりと
色々な事が書かれています。
本書のポイント

深い当事者研究
本書は「論文」の様式で書いた章で、
医療や福祉の分野の専門家ではないとしつつも、
それらの諸分野のさまざまな文献を使いながら自身の事を説明しています。
これは筆者のある考えによるものです。
筆者は発達障害の医療的事実に関して、
診断を下したかつての主治医に色々な質問をしたが、
満足のいく回答は得られなかったと言っています。
また福祉の支援者には福祉に関する色々な質問をしたところ、
満足のいく答えを多く得たものの、
自助グループに関しては自分が当事者として得た知識が決定的だと感じたと述べています。
自助グループに関する指摘として、
当事者の「体験知識」は医療や福祉の専門家による「専門的知識」に匹敵する
という見解があります。
筆者はこの部分に共鳴し、Ⅱ部で当事者として体験知識を語っています。
この部分は筆者の体験に対する深い考察がなされており、大変参考になります。
すべてを紹介したいところなのですが、
今回は2つに絞ってお伝えします。
「魔法の世界」と表現しているもの
この著書で引用されている村上靖彦は、
「自閉圏の人から見ると、定型発達の習慣は全くの異文化である」、
「アスペルガー障害の人は、異文化に住んでいるが、自分の文化は理解してもらうことができず、
文化が違うということすら知られていない。場合によっては自分でも定型発達とは異なる文化を
生きている事に気がつかないまま、ずれから来るトラブルに苦しんでいるかもしれない」
と指摘しています。
こうした異文化をパワン・シンハらは魔法の世界と表現しています。
この世界は「魔法」が次々と発生し、
しかもそれを自分では制御も運用もできない世界です。
ASDは出来事の予測がしずらく、物事がデタラメに起きているように体感されるため、
世界が秩序だったものではなく魔法のように現れると説明がなされています。
筆者はこの原因を
感覚過敏や過集中によって感情が上手く処理できず心理的に無防備になることで
魔法の世界に投げ込まれている感覚になるような気がするのではないか
と考察しています。
そのような魔法の世界で生きているという事を
支援者は理解する必要がある事が分かりますし、
発達障害当事者の方の生活を考える上で非常に重要なポイントだと思います。
脳の多様性について
筆者はこの本の随所に、
私たちは脳の多様性を生きていると述べています。
筆者は色々な仲間と交流し、自己の理解を深めていく事で、
ASD・ADHDと診断された自身ならではの個性もあり、
またASDもADHDも多様であると思い知ったと述べています。
医学的診断基準(DSM-5)に書かれているADHDの不注意の項目は
脳の多様性が認められて社会が寛容になる、
またはADHDの方を想定したセキュリティシステムが導入されれば
全て解決する問題です。
筆者は未来の診断基準についてある希望を述べています。
それは医学モデルと社会モデルの総合の先にあるものなのですが、
社会モデルが強化されることによって、
脳の多様性が広く認められるべきだと考えています。
DSM-5は障害の発生源を個人に診ています。
ここから社会モデルとの総合が進むことで、
ある障害が社会の責任だとする一方、
個人にもその責任が向かっていく危険性があり、
結局は問題発生の要因を個人に押し付けられる危険性を指摘しています。
個人にのみ障害を結論づけるべきではないと考えています。
こういった考察が大変深く考えさせられるものばかりです。
脳の多様性はこの本で筆者が伝えたい核となる考えであり、
本書の重要なポイントです。
ここに書ききれない内容がまだまだたくさん載っています。
感想
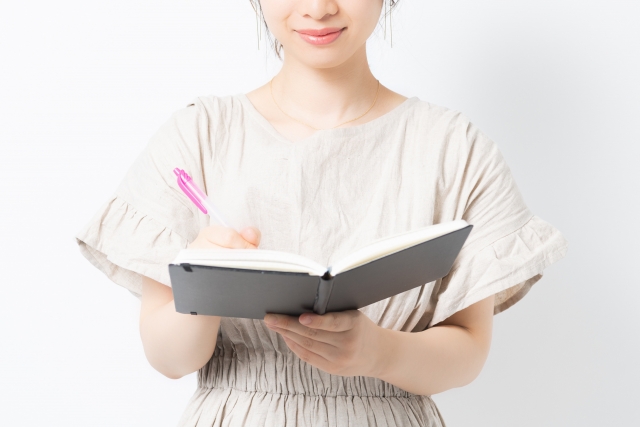
当事者研究の本に詩と小説が入っているものに私は初めて出会いました。
詩については、
筆者は自分の言語で思考して話をすると
詩的な表現になるのだと書いています。
発達障害の方は本当に個性豊かで色々な人がいると毎回思わされるのですが、
「同じ日本語の文法を扱っている」と当たり前に思っていた前提ですら
一度離れて考える必要があるのだなと思いました。
すごい発見をしたという感覚です。
また、本書は感覚統合についても少しだけ書かれています。
筆者が持つ感覚や脳の特性から、
よく水の中にいると感じられる時があるとの事ですが、
もし脳の可塑性が高い子どものうちに感覚統合療法を受けていれば
この特別な感覚を失っていたかもしれないと思っており、
それであれば受けなくて良かったと思うと述べています。
この文章は非常に考えさせられます。
私も含め療育に携わる人は、子どもたちの将来を考えると
今やっておいた方が良いと思いながらやっている事でも、
実は子どもたちからすれば必要のないものだと思っている事がある
という事です。
過去にもこうした事例は何度か見聞きしたり経験もあるのですが、
この本を読んではっきりとしたと感じています。
子どもたちに寄り添うとはどういうことなのか
私にはまだ明確には言えない事もたくさんありますが、
私の中心的な考えになることは間違いないですし、
これからの療育の姿勢が変わっていくと強く感じます。
まとめ
著書「みんな水の中」は
発達障害の当事者の方が自身の体験世界を知る上で
大変参考になります。
それに脳の多様性について考える大変貴重な1冊です。
当事者の方たちがどのような文化で生きているのかを知りたいと思った方は
是非お手に取ってみて下さい。


コメント